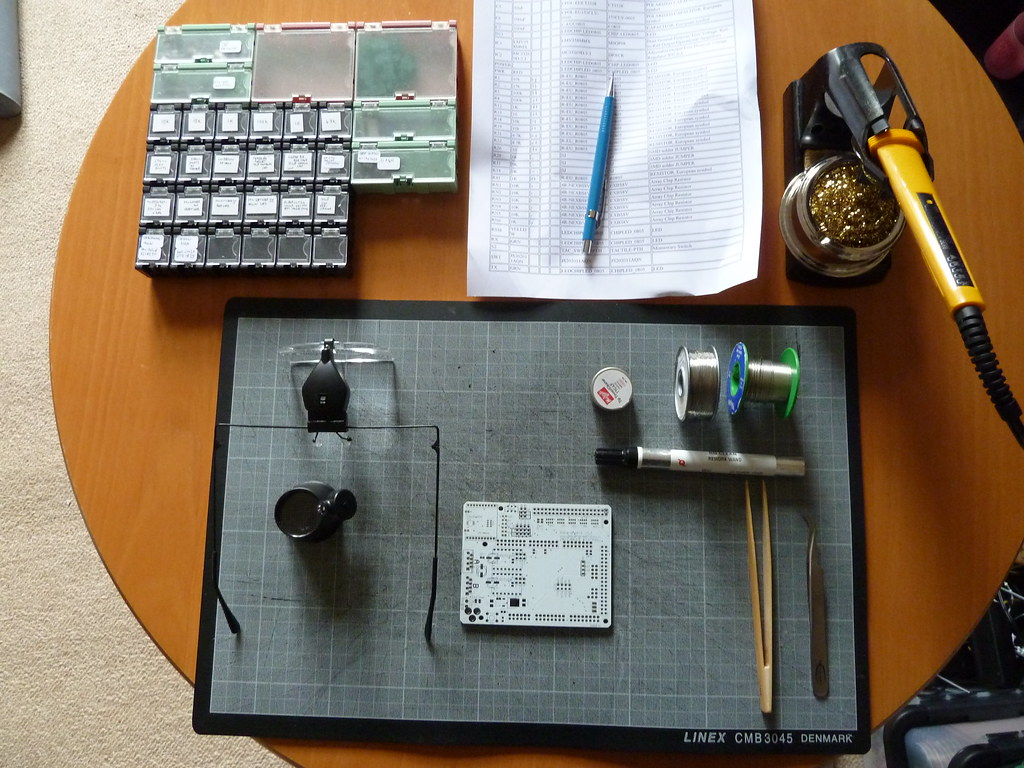購入前から分かってはいたのですが「安いはんだごて」はこて先の温度管理を自分で行う必要があります。ちょっと高いモデルですと本体にダイアルが付いていたりして温度調整が出来るのですが私の購入した安物には当然、そんな機能はありません。それでも工夫すれば何とでもなりますよ!
¥681 (2023/03/10 20:35時点 | Amazon調べ)
目次
慣れているならこて先の掃除
こて先の温度が上がり過ぎてハンダが上手く出来ない場合はこて先の温度を下げる必要があるのですが、こて先を濡らしたスポンジで掃除する際に当たり前ですが温度が下がります。温度が上がり過ぎかな?と感じた際はこて先を冷やす為に汚れていなくてもこて先をスポンジに擦り温度を下げます。ハンダ付けの数が少ない場合はこれでも誤魔化せますが数が多い場合はちょっと面倒でこの方法はお勧め出来ません。
はんだごての電源を入り切りする
誰でも考えつく事ですが中間スイッチを入れて温度が上がったら「切る」、下がったら「入れる」という方法です。我が家はこの製品を他で使っているので試して見たのですが意外に面倒に感じました。もう少しスイッチを手元付近に置けば感想も違ったかもしれませんが集中してはんだづけをしているとスイッチの入り切りは案外、億劫うな物です。
¥623 (2023/03/10 20:54時点 | Amazon調べ)
ネットでは良さそうなアイデアも
何か良い方法は無いものかと調べていると上手い方法が見つかりました。仕組みは所謂「半波整流」なのですが100均のスイッチ付タップにダイオードを追加して温度を上がらなくする方法です。しかしこの方法はどちらかと言えばはんだ付けの途中で電源を切らずにこて先の温度を下げ過ぎないで保持する目的ですね。それでもこれは良いアイデアと思います。費用も格安ですしシンプルなだけに安心です。